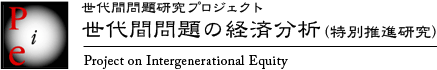研究の必要性
分配をめぐる対立軸は、かつては地主と小作人、商人と製造業者、資本家と労働者、市場経済国と社会主義経済国、経済先進国と発展途上国、男性と女性、などにあった。しかし今日、その主要な対立軸は地球温暖化や年金・医療・雇用・子育て・教育・赤字財政・技術革新などの問題にみられるように世代間にあると確信している。ただ、そのような研究の社会的重要性や緊急性はきわめて高いのにもかかわらず、総じて研究の蓄積状況は今のところ質・量ともに十分とはいえない。問題の設定そのものが比較的新しいこと、および関連するデータが十分に整備されていないこと、の2つにその理由があり、世代間問題の研究を継続することの高い必要性はまさにこの点にある。
分担研究課題別の研究必要性は以下のとおりである。
(1)世代間問題という新しい切り口から年金問題を分析すること(本研究では高山が担当する)は今や世界の常識である。ただ、その問題を克服するための具体的手法は未だ開発途上にある。課題先進国である日本がリード役となって、その問題克服方法を具体的に提示することは単に学術上の多大な貢献となるだけでなく、地球的規模で社会的緊急性をもつ懸案を解決することにつながるだろう。
(2)クープマンス=ダイアモンド型の世代交代モデルにおける情報的基礎は世代効用の無限流列である。だが、将来世代の可塑性を考慮すれば、世代効用の無限流列に関する情報は現在世代以降の選択行動系列次第で可変的であり、従来分析を機械的に適用できない。また、サミュエルソンの世代重複モデルでは、あらゆる世代が基本的に同一の世代効用関数を持つと仮定されているため、将来世代の可塑性を導入すれば、分析の基本的骨格自体を本格的に再構成することが必要となる。地球温暖化問題や代理懐胎の問題の難しさは、将来世代の可塑性を無視できないことにある。この点において、鈴村が担当する世代間衡平性の厚生経済学をこの難問に向けて拡充する必要性・緊急性はきわめて大きい。さらに社会的な時間割引率に関する既存研究はいずれも動学的一貫性の欠如が問題とはならない枠組(今日立案した計画に未来永劫にわたりコミットするのが可能な環境)の中で、個々の消費者の効用関数が時間加法性を満たす場合を想定している。動学的一貫性や時間加法性を満たさない効用関数に既存の研究結果を拡張しようとする原の研究は、この点で先駆的である。その意義は、年金資産の運用など現実への幅広い適用可能性にある。
(3)玄田が発表した雇用の世代効果に関する研究(「チャンスは一度:世代と賃金格差」『日本労働研究雑誌』1997年10月号)をきっかけにして日本国内で多くの研究がなされてきた。米国では低学歴者の就業条件が景気の一時的変動によって左右されやすいのに対し、日本の低学歴者については、不況期に卒業したことによる就業条件の低下が景気回復後も持続する(Genda, Y. et al.“The Endless Ice Age,”The Japanese Economy, Fall 2008)。このように労働市場と景気変動において、他の先進諸国にない特有な構造が日本にある。1990年代後半以降、日本の失業率は急速に上昇し、特に若年層の失業率は大幅に上昇した。若年をめぐる就業状況の変化は、当時、多くの場合、若年本人の労働意欲低下など、労働供給側に原因があると考えられることが多かった。それに対し、本研究プロジェクト雇用班では、若年世代の雇用状況の悪化は、日本の労働市場に特有な世代効果や、各組織における中高年雇用者の雇用を維持する代償として若年採用が抑制されるなど労働需要側にこそ、真の原因があると考えてきた。ただし、2000年代における中高年世代の希望退職増加、企業による非正規雇用者の重用、学校による新卒者への就職斡旋の停滞などを受け、雇用の世代効果や置換効果などに一定の変化が生じている可能性がある。とくに2008年秋の世界不況以降、日本の就業状況はかつてないほど深刻化することが懸念されており、なかでも若年世代の就業困難が予想されている。つまり、2000年代を通じて起こった労働市場と企業組織の構造的変化を世代という観点から明らかにしていくことが緊急に求められており、その研究成果は、今後における雇用政策の立案・実行にとって有益な情報となるだけでなく、企業内の人的資源管理にも役立つと考えられる。また多くの人々の希望喪失は、近年の最も深刻な問題である。就業や生活への希望がどのように形成され、それが世代によってどのように異なり、さらに世代間でいかなる相互作用があるかを明らかにすることも、希望を一つの視点に加えた世代研究への強い期待につながっている。その成果はキャリア教育などに対して重要な情報を提供するだろう。いずれにせよ低成長による限られた雇用機会をどのように世代間で分配するのかが、ますます重要な社会的課題となっており、雇用に関する世代対立を世代協調に転換するアイディアを提示することは学術上、多大な意義と価値をもつと確信している。
(4)高齢者人材の有効活用問題を共有する先進国では米国のHRSが1992年から、英国のELSAが2002年から、大陸欧州のSHAREも2004年から11カ国でそれぞれ実施されている。中でも先駆的なHRSはミシガン大学が中心となり、約2万人のサンプルに対して1回あたり数億円、1人当たり数百ドルを投入する調査である。この国際コンソーシアムに日本もJSTARとして参加しており、その継続必要性は、きわめて大きい。
(5)若年層の貧困・疾病リスクやそれが子供の健康や教育達成、成人後の貧困・疾病リスクに及ぼす影響、あるいは健康意識や幸福感への影響に関する実証研究は、高齢者の健康や就業・引退行動についてのそれに比べると、かなり出遅れている。また、「子供の貧困」問題は、健康科学、社会学、教育学、経済学などによる学際的な研究テーマであるにも拘わらず、従来の分析はそれぞれの研究領域で個別に進められてきた感が強い。本研究では、様々な研究領域で蓄積されてきた知見やアプローチを総合的に活用することにより、「子供の貧困」問題の実態を解明し問題解決のための効果的な子育て支援の在り方を探る。不安定な就業状態・所得環境に置かれた若年層が子育ての面で不利な状況に置かれ、しかもその影響が子供に及ぶという傾向は深刻な社会問題となっている。子供たちに機会均等を保証し、階層の固定化や貧困の連鎖を回避するためにも、「子供の貧困」の発生メカニズムやその帰結を実証的に解明し、その是正策を検討することは、政策的にも強く要請されている。その解明に必要な部分的データは主要国の一部で既に利用可能となっているものの、国際コンソーシアムとして実施される包括的なパネルデータ(LOSEF)は現在、存在しない。課題先進国としての日本がそのようなパネル調査を国際社会に向けて自ら提案し、先行実施する必要性はきわめて高い。そのような研究には次の2つの大きな学術的意義がある。第1に、先進各国で所得格差の拡大傾向や貧困問題の深刻化が一般的に見られるようになっている。この傾向は子育て期における家庭環境の格差に起因する面があるので、動学的な枠組みの中で分析する必要があるが、本研究はその要請に十分対応するものである。第2に、子育て支援の拡充は、社会保障給付のウェイトを高齢者向けから若年者向けにシフトさせることを意味する。また、子育て支援による出生率への影響も社会保障の在り方を考える上で極めて重要なポイントとなる。これらの研究を担当する小塩は、子育て支援と社会保障制度の持続可能性との関係、親の教育需要における階層性、所得格差や貧困の健康意識や幸福感に及ぼす影響などの研究にとりくみ、その成果を内外の学術雑誌に数多く発表してきた。
(6)日本や米国の統計調査等では、子供(回答者)と親の認知能力・職業・所得に関する情報が収集されているものの、子供と親の非認知能力に関する情報は収集されていない。そこで臼井は、親の職業が必要とするスキル項目(社交性、数学、論理力、言語能力等)を職業情報のデータから取り、親と子の職業でマッチさせることにより、親と子のスキルデータを作成する。さらに、スキルを認知能力と非認知能力に分類する。その上で、所得や学歴等の他の要因をコントロールし、非認知能力(特に社交性)が親子間で相関するか否かを検証する。その検証は、学校教育や職業訓練において非認知能力育成の重要度を調べる上で必要である。
(7)欧米では企業負担の医療保険料が賃金の一形態であることが周知の事実となっているが、日本では意見が分かれている(Komamura-Yamada (2004)、岩本・濱秋 (2006, 2008)、Tachibanaki (2008)など)。宮里・小椋(2009)は『就業構造基本調査』の個票データを用いて、先行研究が無視していた非正規雇用の賃金を分析に加えた。この問題の重要性に鑑みて『全国消費実態調査』など別の大規模な賃金・雇用の個票データを用いた実証分析が必要不可欠である。さらに日本ではこの数年間、介護保険財政の逼迫に伴って在宅介護給付が大幅に削減されてきた。しかし在宅介護(とくに家族介護)は施設介護の需要や入院医療の需要の発生を遅らせると考えられ、介護・医療ケアの総費用を抑制する可能性がある。在宅介護給付の抑制政策が続けば、一定期間が経過した後にその反動として施設介護や入院需要が増大するだろう。この在宅介護サービスと医療費との関係はヨーロッパでもopen questionであるとされており、在宅介護の支援政策に経済学的な合理性を付与することができれば、その学術的・政策的な意義は非常に大きい。くわえて、これまで日本における高齢者の医療費が若年者の医療費に比べて先進国の中では特に高いとされ、それを引き下げるため長期入院患者に関する診療報酬の切り下げが次々と実施されてきた。しかし、こうした政策は、一方で行き場のない入院患者を多数生みだし、他方で医師不足や医療崩壊を通じて医療全体の効率性や公平性を大きく損なってきている。重要なことは、なぜ日本における高齢者の医療費が若年者に比較して特に高かったのか、その理由を経済学的に分析することである。そのような分析は現状ではきわめて不十分である。くわえて、日本における公的医療保険給付は疾病・傷病の療養給付に限られており、予防を含んでいない。新型インフルエンザのワクチン接種問題で明らかのように、これから予想される疫病の大流行を前提とすると、予防給付の必要性は大きい。また、日本の公的医療保険制度は、後期高齢者医療制度の廃止が決まる中で組合健保を解散する動きも強まるなど、全面的な再編成を余儀なくされている。保険者を今後どのように再編成するかを考えるためには、公的医療保険者間に医療費リスクがどのように配分されているか、保険者間のリスク調整について単純な罹病率の調整で十分かどうか、経時的な特性に基づいた調整が必要かどうか、などを検討する必要性も大きい。
(8)財政赤字累増に伴う将来の財政負担増は世代間利害対立の大きな一因となる。どのタイミングで増税を行ったり社会保障給付を抑制したりするかで各世代の利得が決まる。そのことが政治過程においても、この間、陰に陽に主要な争点となってきた。日本の政府債務残高対GDP比は2010年代には200%を越える見通しであり、これは平時の先進国では記録したことのない異常な状態である。こうした未曾有の財政状況に直面している日本が近い将来においてどのように財政赤字を抑制し財政健全化を行っていくべきかを検討することは喫緊の課題である。ただ、財政政策は多分に民主主義の影響を受ける。経済学的に正しいとだけ唱えても、その政策提言は受けいれられない可能性が高い。政治的実現可能性を上記の分析と整合性のある形で考慮する必要がある。さらに政治過程における有権者・政治家・政党・官僚・圧力団体等の各々の主体についてゲーム理論的・公共選択論的な分析が近年でも多くなされてきた。しかし政治過程における主体間の戦略的な行動を明示的に扱った財政政策のマクロ経済への効果は、今後もさらに深く究明する必要がある。くわえて税制改革や地方分権改革はこれまで世代間問題として捉えられることが少なかった。しかし、今や財政赤字(公債の発行と償還)を通じて、税制がもたらす効果も、国と地方の財政関係にまつわる効果も、世代を越えた利害対立を顕著に生じさせるものとなっている。それを克服するには世代間の利害調整が適切に行われる必要がある。
(9)青木は知的財産、特に特許制度の理論分析をAER, IJIOなどの査読誌に掲載してきた。OECDを含む海外の関連コンファレンスにも招待されている。青木は、技術投資と人的投資の補完性をとらえた技術革新促進制度分析のフレームワークを構築し、日本の少子高齢化環境における望ましい制度を新たに提案する。少子高齢化への対応は炭素ガス排出抑制・地球温暖化対応と並んだ急務であり、有効な技術革新促進の制度設計が必須である。さらに青木は選挙制度と再分配の関係を分析する。人口構造の変化を考慮し、P. Demeny, W. LutzらはDemeny 投票法と呼ばれている選挙制度を考案したが、日本でも大竹文雄や金子勇が独自の提案をしている。さらに井堀利宏・土居丈朗や実業家の冨山和彦・松本大等が新しい選挙制度を提案しているが、日本の政治学者による議論は今のところほとんどない。そこで、日本の政治学者に本研究への協力を促し、政治経済学的アプローチの共同研究班を編成する。世代間の資源配分には投資を通した異時点間の外部性があり、その適切な配分は政治的なリーダーシップがなければ実施できない。欧米に比べてまだ遅れていると思われる選挙制度に関する政治経済学的な研究を始動させることは緊急課題である。
高山を中心とする本研究チームは、平成18年度より世代間問題の経済分析を推進してきた。この間、期待以上の研究成果を挙げてきたと自負しているものの、研究計画を再構築して研究対象を拡大し、研究水準を飛躍させる必要性を痛感している。これが、特別推進研究に応募した理由である。